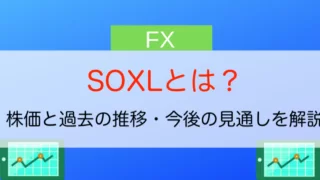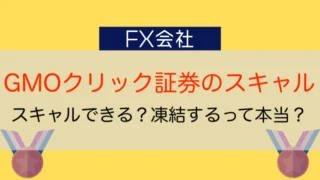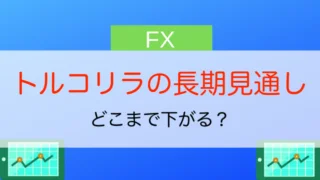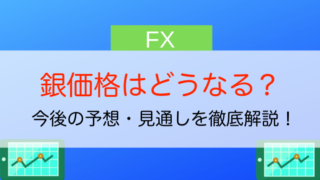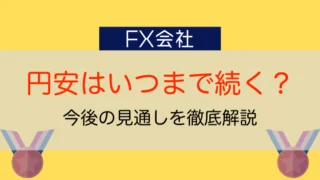今回は「FXと日銀の金利の関係」について、詳しくまとめていきます。
2024年3月19日の金融政策決定会合で、日銀は長らく続けてきたマイナス金利の解除を決定しました。
約17年ぶりとなる利上げに、為替市場の動向にも大きな注目が集まっています。
しかし、FX初心者のなかには、このような金利と為替レートとの関係性についてまだよく分かっていない、という方も少なくないのではないでしょうか?
そこでこの記事では、FXの予測に必須ともいえる「日銀の政策金利」について、基礎知識から徹底解説、さらにそれを活かしたトレード手法についても紹介していきます!
- 日銀は民間の金融機関とはまったく異なる「銀行」
- 金融政策で物価や金融の安定をはかる
- 為替相場の行き過ぎたトレンドを抑制
- 政策金利はインフレ率によって決まる
- FXでは通貨ペアの金利差が重要
- トレード手法に合わせて政策金利を活かそう!
FX取引には、デイトレードやスワップトレードなど、さまざまな手法があります。
なかでもシステムトレードは、プログラムに24時間取引をまかせることができ、専門的な知識やテクニックがなくても始められるので、初心者の方にもおすすめです。
今後の政策金利の動向によっては大きなチャンスが訪れる可能性もあるので、ぜひこの機会に注目してみてください!
日銀と中央銀行とは?
そもそも、日銀とはどのような機関で、どのような役割や目的を持っているのでしょうか?
FXとの関係を知るためにも、まずはその基礎知識から見ていきましょう。
日銀とは?
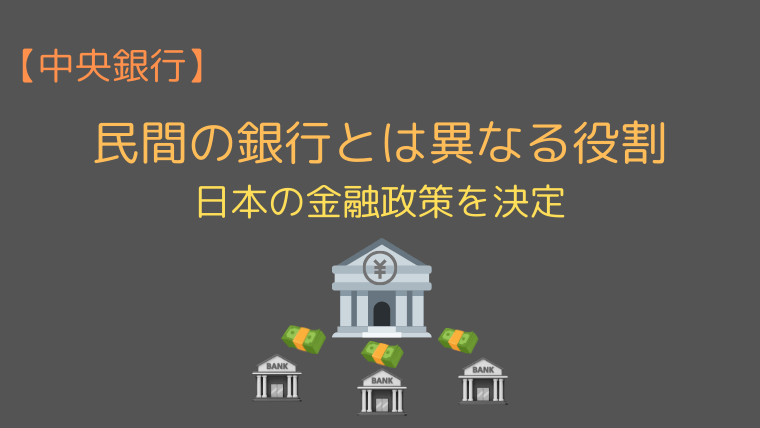
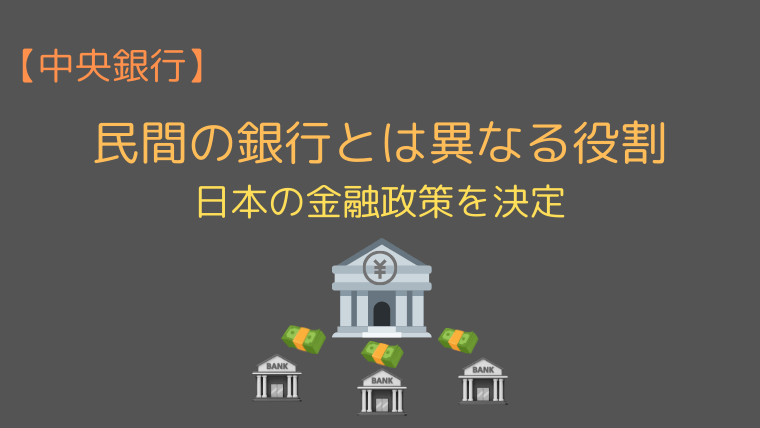
日銀は◯◯銀行
日銀(日本銀行)は、日本国内で唯一の中央銀行です。
「銀行」といっても、その役割はメガバンクや信用金庫など、民間の金融機関とは大きく異なっています。
それを、以下のように「◯◯銀行」と表しています。
- 「発券銀行」…銀行券(お札)の発行・流通・管理
- 「政府の銀行」…国庫金(税金や年金など)の受入・支払、国債の発行・支払
- 「銀行の銀行」…民間の金融機関からの預入・貸出
このように、取引相手となるのは政府や金融機関が中心なので、個人や企業が直接関わることは基本的にありません。
金融政策を決める
日銀のもうひとつの重要な役割に、「金融政策の決定」があります。
金融政策では経済を安定させるために、さまざまな手段を通じて「通貨や金融の調節」が行われています。
なかでも特に重要なのが、以下の2つです。
公開市場操作…国債や手形を市場で売買する
政策金利…短期金利を目標の水準に誘導する
このうち、特にFXに直接的な影響をあたえるのが政策金利で、それをもとに民間の金融機関や通貨の金利も決められていきます。
政策金利は、かつては「日銀が金融機関に預入・貸出を行う際の金利(公定歩合)」のことを指していました。
しかし、1994年の金利自由化によって金融機関が独自に金利を決められるようになったため、現在では「金融機関同士が貸借する際の「無担保コール翌日物金利」の誘導目標」をおもに指すようになっています。
日銀では、政策委員会(総裁1名、副総裁2名、審議委員6名)による金融政策決定会合が年に8回開催され、そこで政策金利の方針も決定されています。
中央銀行とは?


物価・通貨の番人
日銀以外にも、多くの国にはそれぞれの「中央銀行」が設置されています。
国によって形態や役割に違いはありますが、「通貨や金利を調節することで、物価や金融システムの安定をはかる」という目的に関してはほぼ共通しています。
各国の中央銀行には、以下のような例があります。
- アメリカ…中央銀行という組織はないが、連邦準備制度理事会(FRB)が主要都市の連邦準備銀行を統括するかたちで金融政策を決めている
- EU…欧州中央銀行がユーロ圏20ヵ国の統一した金融政策を決定し、各国の中央銀行がそれに従って調節を行っている
- イギリス…17世紀の対仏戦争で、国債の管理を行う商業銀行として設立されたイングランド銀行が、歴史を経て中央銀行としての役割を担うようになっている
主要国の中央銀行トップは、その重要性から、国際的な経済・金融問題について話し合われる「財務大臣・中央銀行総裁会議(G7・G10・G20)」にも参加しています。
政府からの独立
中央銀行のもうひとつの特徴として、その多くが政府から独立した機関となっていることが挙げられます。
なぜかというと、政府は物価の安定よりも、財源の調達や雇用の促進のためによりインフレ(物価上昇)志向の政策を求める傾向があるからです。
中央銀行にはそのストッパーとしての役割もあるので、政府から独立して圧力を受けにくくする必要があるわけです。
日本でもバブル崩壊の反省から、1997年に日本銀行法改正によって日銀の独立性と透明性が確保され、現在では政府が55%、民間が45%の出資を行う「認可法人」という扱いになっています。
為替と中央銀行の関係
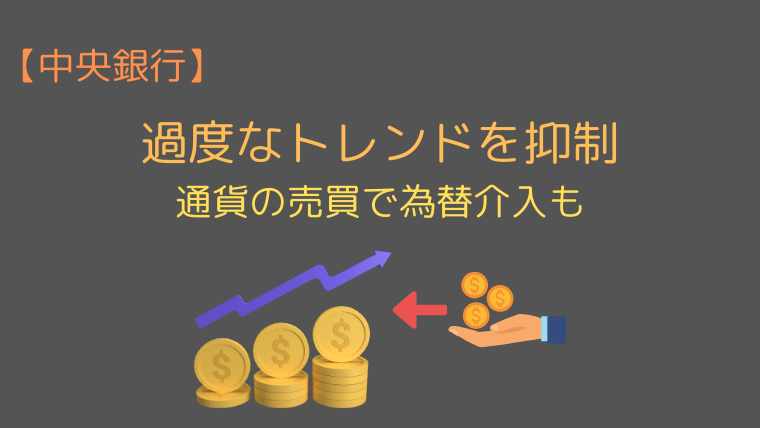
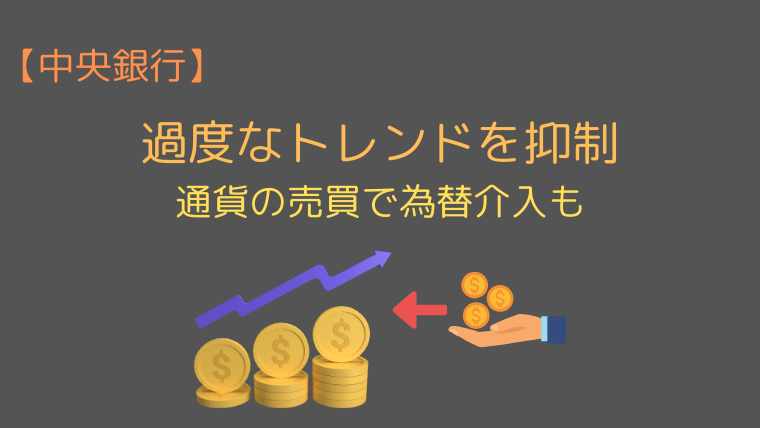
行き過ぎたトレンドを抑える
中央銀行の基本的な役割は、物価の安定をはかり経済に悪影響が出ないようにすることです。
そのため、為替相場に行き過ぎたトレンドが発生している場合にも、それを金融政策で抑えようとします。
日本のように輸出業が盛んな国では、為替レートによって業績が大きく左右されるため、よりその傾向も強まります。
金融政策のなかでも、特に政策金利は為替の動きにダイレクトに影響するので、FXトレーダーの間では常にその動向に注目が集まっているわけです。
直接的な為替介入も
金融政策以外にも、中央銀行が直接通貨を売買することで為替を操作しようとするケースもあります。
このようなやり方を、「為替介入(外国為替平衡操作)」といいます。
たとえば米ドル/円の場合なら、円高に対しては「ドル買い・円売り」でレートを下げ、円安に対しては「ドル売り・円買い」でレートを上げようとします。
ただし先進国では、「為替レートは市場が決めるべきで、為替介入はあくまで例外的な措置とする」という合意があるため、あまり多用できる方法ではありません。
そのため、なかには実施を伏せたまま行われる「覆面介入」や、要人の発言だけで誘導しようとする「口先介入」などもあります。
政策金利とは?
FXと日銀の関わりで、特に重要なポイントとなるのが「政策金利」です。
ここからは、その政策金利を日銀がどのように決めているのか、またそれによって為替はどう影響を受けるのか、などについてより詳しく見ていきましょう。
景気や物価との関係
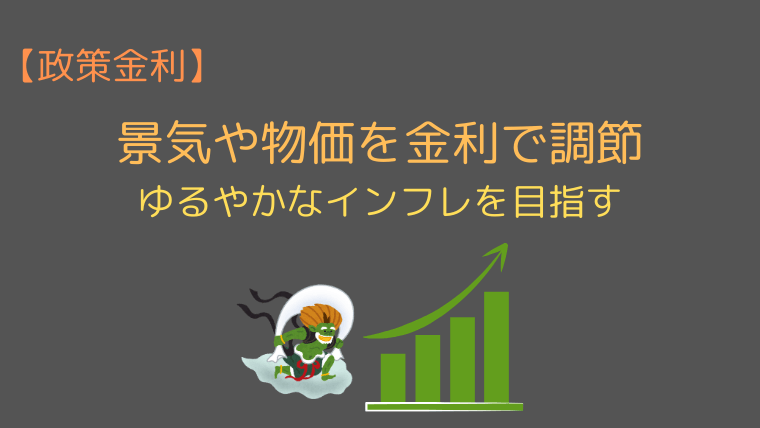
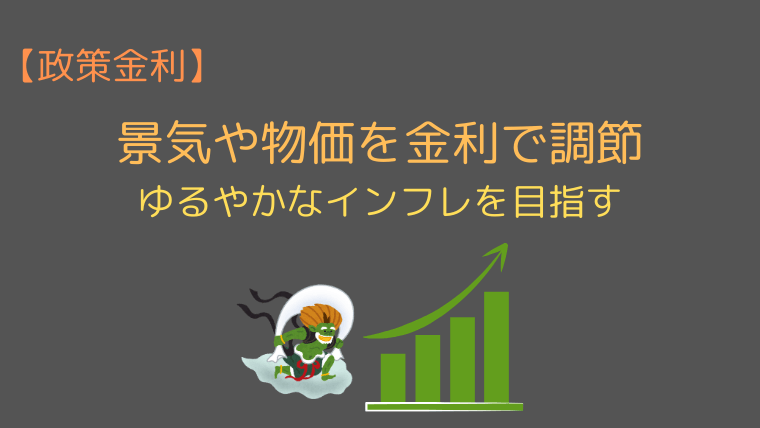
インフレをコントロール
国の経済成長にとって、好景気や物価上昇は欠かせないものです。
ただし、あまり急激な変化が起こると企業や家計に負担がかかってしまうため、中央銀行はそれを政策金利によってゆるやかにコントロールしようとします。
具体的には、好景気ではインフレ(物価上昇)になりやすいため、それを抑えようと政策金利を引き上げ、逆に不景気ではデフレ(物価下落)を防ぐため、金利を下げて景気を刺激します。
大まかな流れを示すと、以下のようになります。
■好景気
→物価上昇
→政策金利を引き上げる
→企業や個人が借入しにくくなる
→設備投資や個人消費が控えられ景気が落ち着く
→物価上昇が抑えられる
■不景気
→物価下落
→政策金利を引き下げる
→企業や個人が借入しやすくなる
→事業拡大や購買意欲の高まりで景気が上向く
→物価下落が抑えられる
日本やアメリカ、ユーロ圏、イギリスなど主要通貨を持つ国は、いずれもインフレ目標を年間2%前後として、それを基準に利上げ・利下げを決めています。
そのため、各国で毎月発表される消費者物価指数は、政策金利の動きを読む上でとても重要な指標となっています。
2000年以降の政策金利
それでは実際に、日銀を中心にこれまで政策金利がどのような推移をしてきたか見ていきましょう。
日本ではバブル崩壊以降、長引く不況とデフレに対し、1999年に世界初となるゼロ金利政策が導入されました。
その後、何度か利上げは行われますが、2008年にリーマン・ショックによる世界金融危機が発生すると、アメリカをはじめ諸外国でもゼロ金利が取り入れられ、日本でも再開することになります。
2015年には、アメリカは景気回復によって利上げに転じますが、日本では不況・デフレがおさまらず、「大胆な金融政策」をかかげる第2次安倍政権のもと、ついに2016年にはマイナス金利の導入に至ります。
2020年には新型コロナの影響で再び世界各国でゼロ金利が導入されますが、規制緩和後の景気回復にともない世界的なインフレが進行、現在では多くの国が大幅に利上げされた状態となっています。
そんななか、唯一マイナス金利を維持してきた日本ですが、物価高や賃金上昇を背景に、ついに今回の解除に踏み切ることとなったわけです。
政策金利で為替が動く
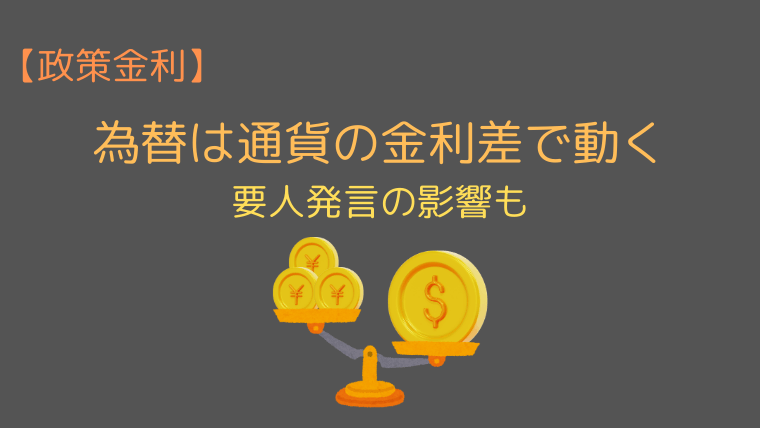
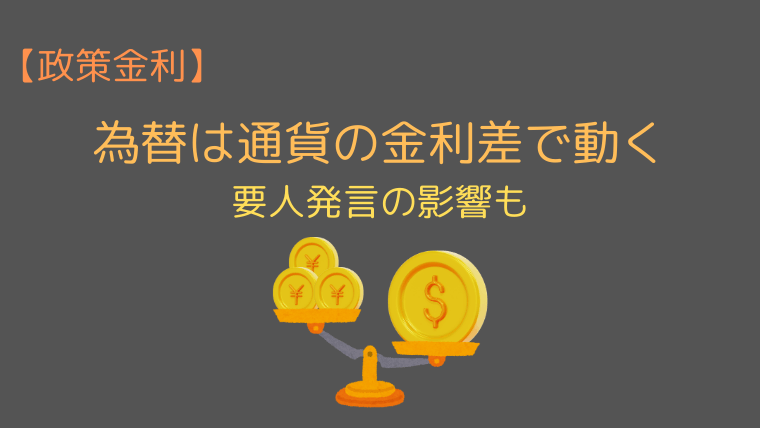
通貨間の金利差がポイント
それでは具体的に、政策金利によって為替がどのように動いていくか見ていきましょう。
まず大前提として、FXでは金利の高い通貨ほど買われやすく、為替レートも上昇する傾向にあります。
FX取引では、日をまたいでポジションを持ち越すと「スワップポイント」と呼ばれる利子のようなものが発生します。
スワップポイントは、通貨ペアのうち金利の高い方の通貨を保有していた場合のみ受け取ることができ、金利の低い方の通貨を保有していた場合は反対に支払わなければいけません。
ただし、金利が高い通貨を保有しているからといって、かならずしもスワップポイントによる利益が大きくなるわけではありません。
FXでは2ヵ国の通貨を組み合わせて「通貨ペア」として取引しているため、スワップポイントもその通貨間の金利差から決められることになります。
したがって、いくら金利が高くても、ペアとなるもう片方の通貨の金利も高ければその差は小さくなり、為替にもそこまで大きな影響は出にくくなるのです。
今回、日銀がマイナス金利を解除したにもかかわらず、あまり円安を解消する方向にならなかったのも、金利が0.10%と依然として低く、5.25〜5.5%の米ドルとほとんど差が縮まらなかったことが原因のひとつとして考えられます。
このように、政策金利が為替を動かすかどうかは、単に金利が上昇・下降したかだけではなく、通貨ペアの金利差が広がったか縮まったかを見ていく必要があるのです。
事前予想や要人発言にも注意
政策金利を見ていくときに、その内容以外にも注意しておきたいポイントが2つあります。
- 政策金利発表の事前予想
- 政策金利の方針に関する要人発言
まず事前予想についてですが、実際に発表された政策金利が市場での予想と異なっていた場合、為替はより激しく変動する傾向があります。
逆に、たとえ利上げ・利下げが決定されても、その水準がおおむね予想の範囲内であれば、そこまで大きな変動にはなりません。
また、その予想を立てる上で重要となってくるのが、日銀総裁や経済閣僚などの要人発言です。
今後の方針にかかわる重要なメッセージなどが発せられれば、それに対する期待や失望から、その時点で為替が動くこともあります。
したがって、政策金利をめぐる事前予想や要人発言などのニュースには、普段からしっかりアンテナを張っておくようにしましょう。
このような発言は経済指標の発表時に行われることも多いので、そちらのスケジュールもぜひチェックしておいてください。
政策金利をFXトレードに活かすには?
それでは最後に、政策金利を実際のトレードに活かす実践法を紹介していきます。
今後もまだ日銀の追加利上げが見込まれるなか、ぜひこのチャンスに利用してみてください!
スキャルピングに活かす


スキャルピングは、数秒から数分という短い間隔で売買を繰り返すトレード手法です。
このスタイルで政策金利を活かすのであれば、金融政策決定会合の発表前後を狙うのがおすすめです。
スキャルピングは短期間で何度も利益を獲得できるのがメリットですが、その反面、値動きも小さくなるので、一度に大きなプラスを期待することはできません。
そこで、短時間でも為替レートが大きく動きやすい、政策金利の発表時が絶好のチャンスとなるわけです。
ただし、値動きが激しいということはそれだけ損失のリスクも大きくなるので、その点には注意が必要です。
リスクを最小限に抑えるためにも、政策金利の発表前から現在のトレンドをしっかり確認して、発表後も1分足や5分足のチャートで動きをつかみながら着実に取引を進めていきましょう。
また、損切りラインをあらかじめ決めておいて、あまりに変動が激しいときにはトレード自体をやめる、といったこともリスク回避として大切です。
システムトレードを活用しよう
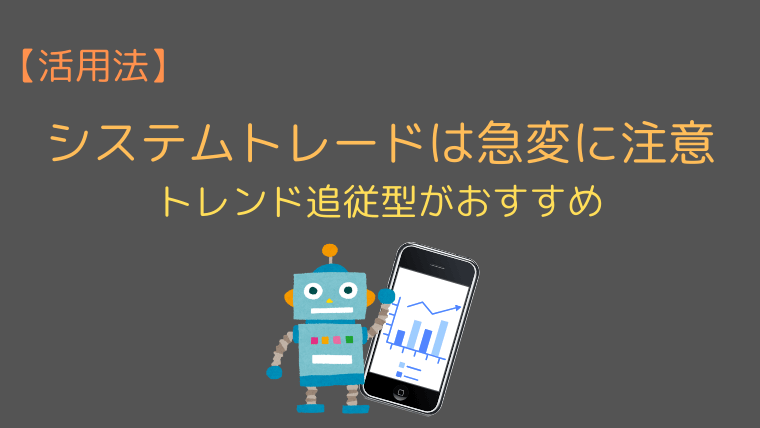
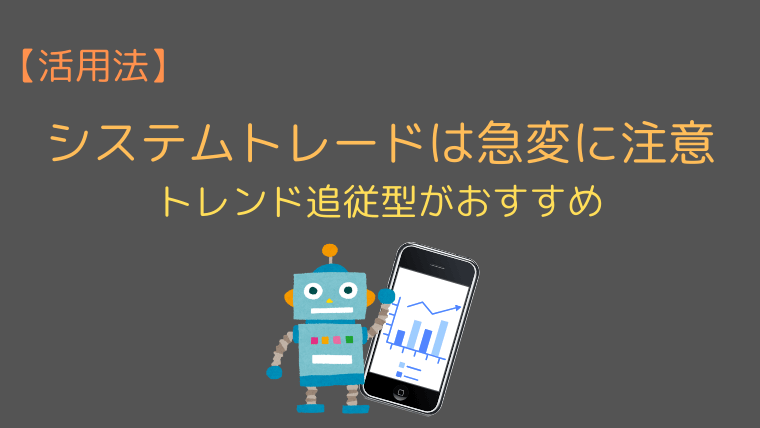
システムトレードは、あらかじめ買値や売値を設定しておくだけで、あとはプログラムが自動的に24時間取引を行ってくれる、とても便利な手法です。
ただし、システムトレードは基本的に為替に動きがない「レンジ相場」に対応したものが多いので、トレンドが発生しやすい政策金利発表時には気をつける必要があります。
まだ初心者のうちは、政策金利の発表時には稼働を停止させておくのが無難かもしれません。
一方で、政策金利の転換によって生まれるトレンドはチャンスでもあるので、トレンド型のプログラムに切り替えることでさらに利益を拡大することもできます。
また、現在ではトレンドの変化に自動で対応してくれる「トレンド追従型」のサービスも増えているので、あらかじめそちらを選んでおくのもよいでしょう。
下記の記事では、各FX会社のシステムトレードのサービスを詳しく比較・紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!
まとめ
ここまで、「FXと日銀金利の関係」についてまとめてきました。
日銀がなぜ・どのようにして政策金利を決めているのか、またそれによって為替はどう動くのか、大まかな流れは理解していただけたかと思います。
政策金利を意識して見てみよう
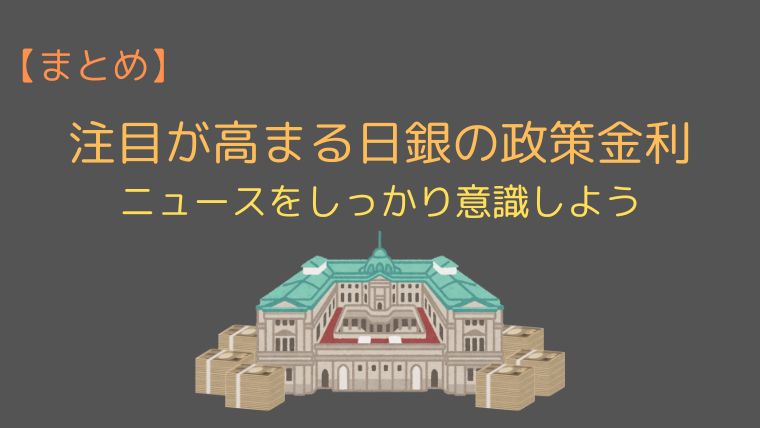
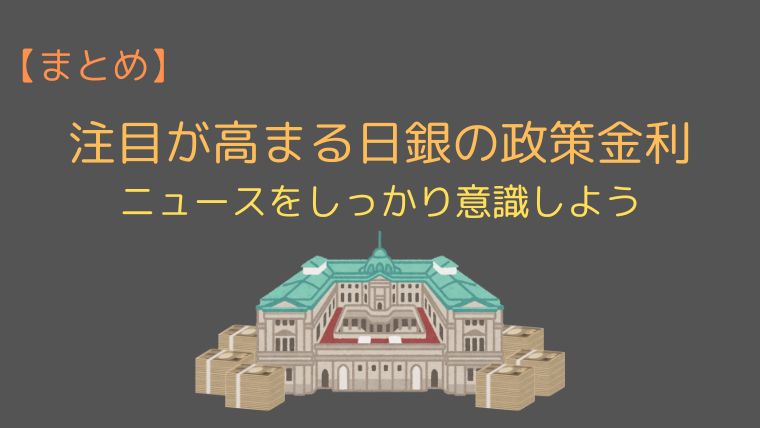
現在、為替市場では、日銀が約7年にわたり維持してきたマイナス金利を解除したことでこれまで以上に政策金利への注目度が高まっています。
いまだ物価高や円安がおさまらないなか、今後も追加利上げが行われる可能性は高いでしょう。
市場の予想や要人発言、また他国の金利も含め、ぜひより強い意識を向けてニュースなどにも目を配ってみてください。
こちらで紹介した、スキャルピングやシステムトレードなどでの実践法を活かせば、さらによい結果も得られるはずです!





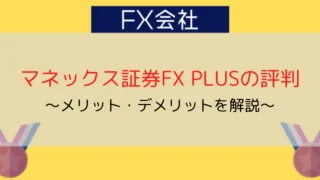
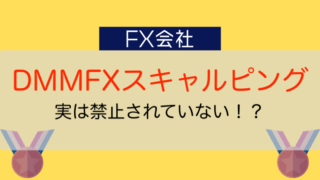



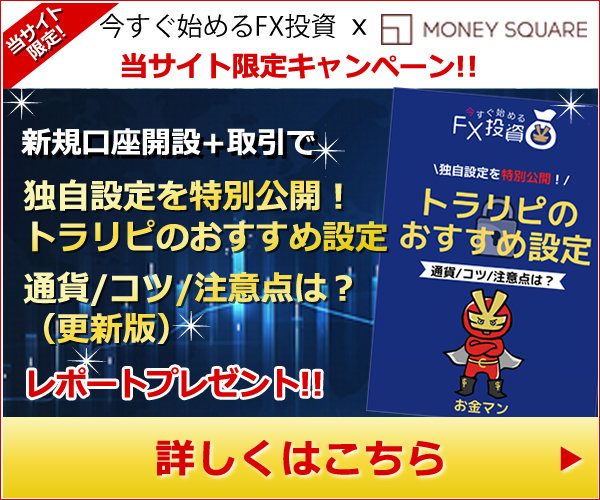
![トレイダーズ証券[みんなのFX]](https://img.tcs-asp.net/imagesender?ac=C100456&lc=PAN1&isq=27&psq=0)